
1)地を這うようにとている

2)大小交互の葉

3)まだ若い感じ

4)根本

5)葉の裏

6)大きいほうの葉

7)裏
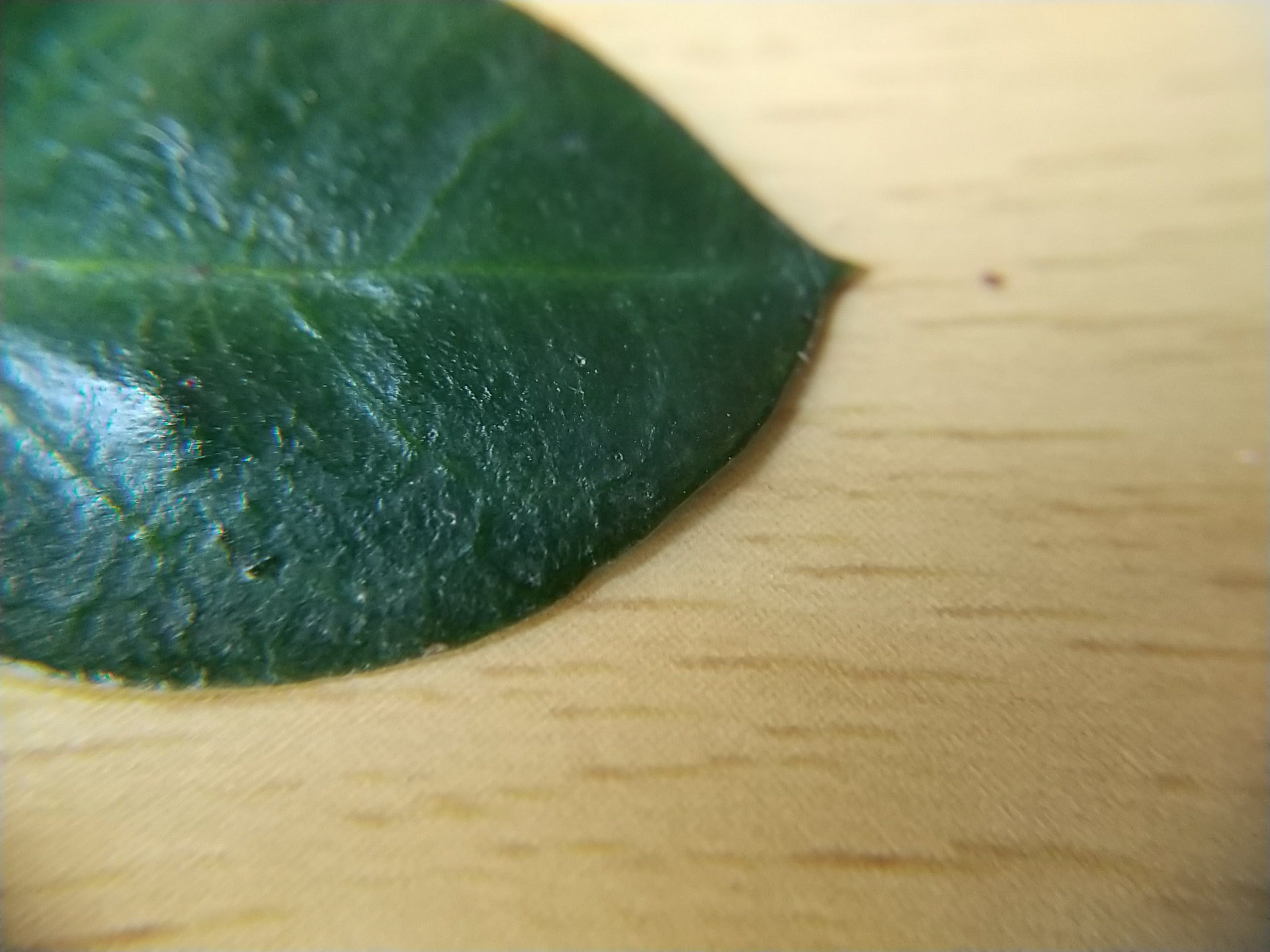
8)てかてか

9)裏は毛がある。

10)これは別の株 D07

11)同じ種と思ったが B05

12)これは違うな。何の樹だろう。

13)B(女坂)の分岐の先の右側

14)新芽

15)よく育っている

16)大きくても腰程度の高さ

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)
オオアリドオシ 大蟻通 別名 ニセジュズノキ
アカネ科アリドオシ属 関東地方以西、四国、九州 常緑樹林内 常緑低木(高さ50~100cmになる) 両性花<3>
葉の長さは2~6cm 針は葉の長さの半分以下<3>
★アリドオシ属は別名・一両と呼ばれる→縁起植物(マンリョウのページ)
★本種はアリドオシの変種とも。オオアリドオシの針は葉の1/3の長さだが、アリドオシの針は葉と同じ長さ
1)-14) E06(西道入口)
13)-15) B(女坂)の分岐の先の右側の株
16) E(西側道)の木道の下の右側の株。これは大きい株だ。だが高さは腰あたりまで。
17)-20) D29(尾根道痩せ尾根)
21)-24) 各所のさまざまな株。実は4月が本番?
25)-28) 花が咲き出した(女坂の群落)
夢中になっている内にどんどん進めます。この森の定点観察第7弾。常陽樹林帯の低木にアオキ以外に何があるか観察してみたら、特徴のある葉をもつ樹をみつけました。大小の葉が交互に付き、棘もある。てかてかして美しいです。3か所で見つけたのでそこそこ生えているようだ。オオアリドオシ。針が鋭くアリも刺し通すから。別名ニセジュズネノキ。実が数珠のように付くジュズノキに似ているから。これはまだ若い樹のようなので、実がなるかなあ。
11)12) 3か所と書いたが、そのうちの一つは、大小の葉で棘があるのは同じだが、葉の質感が違っていて、同じ種類ではないようだ。樹高もオオアリドオシにしては高すぎる。こっちは何だろう。次から次へと疑問が出てくる。(8/27)
13) テレワーク前のこの森散歩。まだまだ暑いが、尾根に出ると涼しい風が吹いてきます。ヒトの眼というものは(自分だけかもしれないが)、おかしいもので、昨日、3株のオオアリドオシを見つけたと書いたが、そのせいなのだろう、今朝のこの森はオオアリドオシだらけ。確かに照葉樹林帯に限られているがあちこちに群落のように生えていました。見るものすべてがオオアリドオシのような気がするほどです。見事に大小の葉が交互ですね。小さな葉が可愛いです。(2020/8/28)
17)-20)
常緑樹の赤い実。一両、十両、百両、千両、万両とある。昨日は万両を紹介したが、今日は一両です。この樹は、すでに紹介済みだが、オオアリドオシです。この森では、大変多くみられる小木です。しかし、実をつけているのはあまりない。やっと実を見つけたのがこれです。なぜこれが一両という別名があるかはよくわからないが、「千両,万両,有り通し」と、マンリョウとセンリョウと、このアリドオシを正月に並べて縁起をかついだとか。千両も万両も有り続けてお金に困らない、ということだとか。 あとは、十両、百両、千両を探さなきゃ。(2021/1/5)
<実の本番はなんと4月??>
21)-24) いよいよGWだが、旅に出るわけにもいかず、仕方ないのでこの森でゆったりしようかと思っていたが明日は大雨ではないか。いろいろ確かめたい樹があったのだが、読書三昧だな。で今日は、花ではなくちょっとした驚きの写真です。これは数日前のもの。オオアリドオシの実です。普通は1月に実が色づくはずで、1月5日にこの樹の実を紹介したのですが、その時はほんの少ししか実が付いていませんでした。この森にはオオアリドオシはかなりの数が生えているのですが、ほとんどが実がなくおかしいなあと思っていたのでした。しかし4月になって多くのオオアリドオシの樹に実が目立つようになりました。どうしちゃったんでしょうか。いくら暖冬だったとはいえ。本来はそろそろ花が咲く時期なんですが。この森には不思議なことがいっぱいある。(2021/4/28)
<そしてすぐに花が咲いた>
25) GWも"この森"三昧。樹の花を探して歩きまわっています。いろいろ咲いていて飽きることがありません。先日、オオアリドオシの季節外れの赤い実を紹介しましたが、もう花をつけていました。あれあれいつの間にやら。下を向いているので、下から覗いてみましょう。
26)27) オオアリドオシの花を正面から。造花の様な端正な花ですね。雌しべが面白い形をしています。
28) オオアリドオシの花を横面から。なかなか美しい花です。(2021/5/2)
■課題
E(西側道)の入口から木道までの右側、E(西側道)降口から少し先の右側、B(女坂)の分岐の先の右側などに集中的にあり。分布に偏りがあるのはなぜだろうか。
2021年度はなぜ4月になってから実が付き始めたのか。花はいつ咲くのか。
1)-9)2020/8/26 10) 8/23 11)12)8/26
13)-16) 8/28 17)-20) 2021/1/3 21) 2021/4/4 22)-23) 4/11 24) 4/24 25)-28) 5/2









